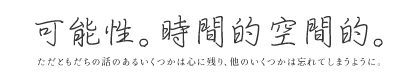ロフトワーク林さんと、わくわくする企みごと。
2013年、奥多摩の森を舞台に事業をはじめた株式会社東京・森と市庭。そこにいちばん最初に遊びに来てくれたのは、ロフトワークというちょっとへんな会社でした。その夏の合宿の様子はロフトワークさんのブログをご覧いただくとして。それから数カ月後、奥多摩の紅葉真っ盛りの秋、ロフトワーク共同創業者の林千晶さんを訪ねました。トビムシとロフトワークという、ひと言では説明しづらい会社の代表同士が、合宿のこと、お互いのこと、これからのことを話しました。
(この対談は2013年11月におこなわれました)
画像提供:ロフトワーク
第4回 クリエイティブの力、愛される場所
 林
林ところで、私、前から聞きたかったんだけど、
竹本さんって、法律とか金融とかが専門で、
ビジネスデザインをしている人じゃない?
その竹本さんが、クリエイティブの力を使って、
プロダクトをつくっているのがとても興味深くて。
ビジネスの人は、ふつうはデザインからはすごく遠いのね。
デザインされたものをみても「おもしろいですね、きれいですね」
とはいうけど、あまり関心がないのね。
竹本さんは、なんでクリエイティブの力を信じてるの?
それがすっごい不思議。
前から聞きたいなと思ってたの。
 竹 本
竹 本うーん・・・、
まず、大前提として、地域が地域として持続可能であるために、
中央集権的な構造を変えて、地域が自立的に、
自ら、投資家や顧客やビジネスパートナーをつくっていかなきゃいけない
という問題意識があるよね。
 林
林うん。
 竹 本
竹 本でも、例えば、ものを動かす時に、
鞘(さや)を稼ぐようなやり方では、
量を増やす、タイミングを早くするということでしか競争できない。
それでは、構造が何も変わらない。
そうすると、そこにあるものを活かすしかない。
日本の中山間地に多くある資源は、やっぱり森であり木。
特に木は、もともとは半分が水分だから、
動かす距離を極小化しなきゃいけない。
木を動かす距離がのびたら、その時点で負け。
だからできるだけその土地で価値ある商品にしなければいけない。
 林
林なるほどね。
 竹 本
竹 本B2C(一般の生活者向けのビジネス)でいうと、
その地域で、触れてもらう、知ってもらう、
楽しんでもらうことができないといけない
森に来てもらえれば、みなさんファンになってくれる。
そうすると、持って帰れるものがほしくなる、
家になにかを持って帰ってもらうと、
森と自分の同期性がキープできる。
マクロ的な構造を変えていくためにも、具体的なモノ、
その地域ならではの、デザインされたプロダクト、サービスが必要。
 林
林なるほど、良いデザインじゃないと、いけない。
 竹 本
竹 本そうそう。
わくわくする、触りたくなる、持って帰りたくなるもの。
 林
林でもさあ、とは言え、国内だと、
単価はどうしてもあがっちゃうじゃない?
 竹 本
竹 本それは仕方ないので、一定の時間軸の中で
解消しないといけないと思ってる。
西粟倉でも黒字化に3年かかった。
黒字化のポイントとやってきたことを考えてみると、
まず、通常の流通に乗せると絶対にうまくいかないから、
エンドユーザーのお客さんを増やしていった。
最初はもちろん赤字なんだけど、地域のファンが増えてくると、
それを魅力に感じる企業が一緒にやりたいと言ってきてくれる。
うちの商品や価格ありきで商品や取引を考えてくれる。
一定の時間軸の中で、エンドユーザーが増えていることを背景に、
BtoCはもちろん、BtoB(企業間取引)も増える。ということ。
そこは、どんなにがんばっても、1年じゃ絶対できない、
最短でも2年、3~4年はかかると思う。
エンドの人たちをどう巻き込んでいけるか、という流れだと思う。
プロダクトだけじゃなくて、プロセスもコンテンツだし、
そこに集っているたくさんの人たちの賑わいが価値そのもの。
まさに、ロフトワークが奥多摩で合宿やってくれたみたいに、
クリエイターの人たちの発想とか対話とか。
だから事業の持続可能性にとって、
クリエイターは必要不可欠だと思っている。
 林
林なるほど。私もね、
ファブカフェをはじめてから1年半くらい経つけど、
ファブカフェを「レーザーカッターが使える場所」ってだけ
にしなくてよかったなーと思ってたの。
レーザーカッターや3Dプリンターが使えるところって、
以前は全くなかったけど、この1年半の間にものすごい増えた。
いま渋谷だけでも数か所ある。
もし「使える場所」ってだけだったら、
それが全部競合になっていた。
でも、ファブカフェって、
「新しいものを自分でつくってみたい」っていう
「スピリット」なんだよね。「機能」じゃなくて。
だから、単価で比べられない。
「そういうものを愛してますか?」「愛してます!」
って言ってくれる人たちがいっつも来てくれてる。
今日も朝来たら、東急ハンズの袋をもって、
開店前から並んでる子たちもいるの。
 竹 本
竹 本へえー、すごい。
 林
林去年もそうだったの。この季節になると。
卒業制作とかあるからかな。
スタッフに「寒いから開店前でも入れてあげなよ」
ってルール変えたくらい。
こういうふうに「使える場所」じゃなくて、
「愛される場所」になったのが、すごく嬉しくて。
きっと、西粟倉もそうでしょ?
「木の椅子がほしい」っていう人じゃなくて
「西粟倉の物語」を好きになってくれて、
「そういえば、椅子がほしいな。」って時に買ってくれる。
プロフィール紹介
林千晶 Chiaki Hayashi

ロフトワークの共同創業者、代表取締役。2000年に創業したロフトワークでは、16,000人が登録するクリエイターネットワークを核に、Webサービス開発、コンテンツ企画、映像、広告プロモーションなど信頼性の高いクリエイティブサービスを提供。学びのコミュニティ「OpenCU」、デジタルものづくりカフェ「FabCafe」などの事業も展開している。またクリエイターとのマスコラボレーションの基盤として、いち早くプロジェクトマネジメント(PMBOK)の知識体系を日本のクリエイティブ業界に導入。2008年『Webプロジェクトマネジメント標準』を執筆。米国PMI認定PMP。現在は、米国NPOクリエイティブ・コモンズ 文化担当、MITメディアラボ 所長補佐も務める。
1971年生、アラブ首長国育ち。早稲田大学商学部、ボストン大学大学院ジャーナリズム学科卒業。1994年に花王に入社。マーケティング部門に所属し、日用品・化粧品の商品開発、広告プロモーション、販売計画まで幅広く担当。1997年に退社し米国ボストン大学大学院に留学。大学院卒業後は共同通信NY支局に勤務、経済担当として米国IT企業や起業家とのネットワークを構築。2000年に帰国し、ロフトワークを起業。
竹本吉輝 Yoshiteru Takemoto

1971年神奈川県生まれ。横浜国立大学国際経済法学研究科修了。外資系会計事務所、環境コンサルティング会社の設立経営などを経て、2009年、株式会社トビムシ設立。10年、ワリバシカンパニー株式会社の設立に参画。13年、株式会社東京・森と市庭を設立、代表取締役就任。専門は環境法。国内環境政策立案に多数関与。同時に、財務会計・金融の知見を加味した環境ビジネスの実際的、多面的展開にも実績多数。立法(マクロ政策)と起業(ミクロ市場)で双方の現場を知る。